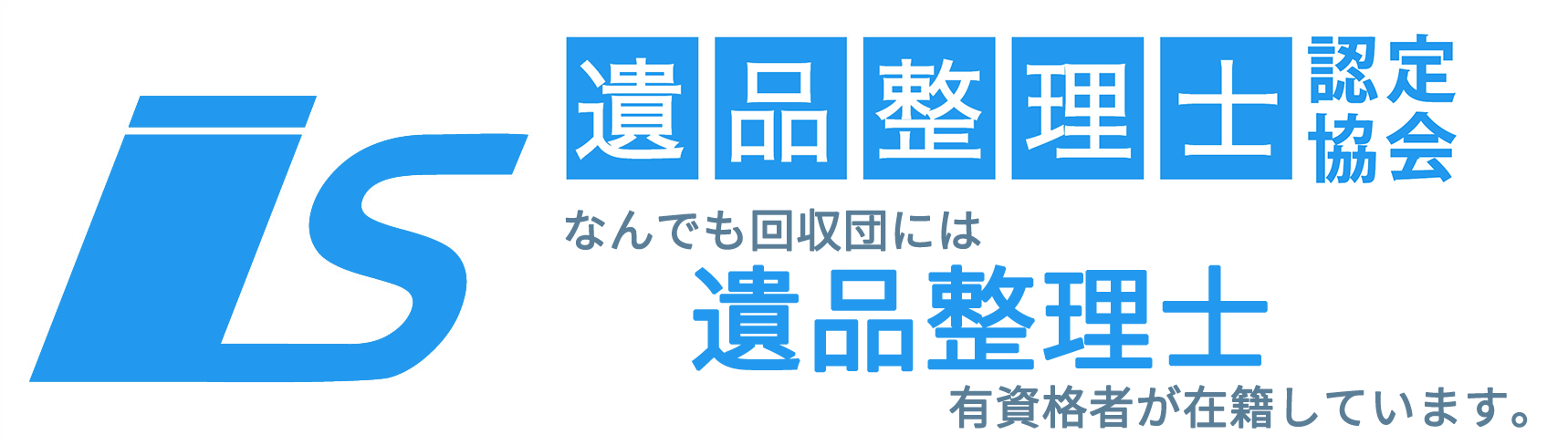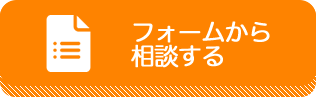骨壺の処分方法を解説します。
本記事では、不用品回収業者や自治体のルールに従った処分方法、供養を兼ねた処理方法など、さまざまな選択肢を詳しく解説します。
この記事を読むことで、骨壺や遺骨の処分に関する具体的な手順や費用の目安、注意点を把握でき、ご自身やご家族が心残りなく適切な供養を行えるようになります。
安心して遺品整理を進めるために、適切な方法を選びましょう。
骨壺の正しい処分方法

骨壺の主な処分方法は、下記の通りです。
- 不用品回収業者に回収してもらう
- 自治体のルールに従って処分する
- 寺院や供養業者に依頼する
- 専門業者に引き取ってもらう
- リサイクル・再利用する
それぞれ解説します。
不用品回収業者に回収してもらう
不用品回収業者に依頼すれば、骨壺を迅速かつ安全に処分できます。
一般的に、回収業者は遺品整理の一環として骨壺の回収を行い、供養や適切な処理を提供する場合もあります。
特に自治体のルールでは処分しにくい大きな骨壺や陶器製の骨壺も、業者なら柔軟に対応可能です。
費用は3,000円~10,000円程度が相場で、供養付きのサービスを提供する業者もあるため、事前に確認すると安心です。
自治体のルールに従って処分する
自治体によっては、骨壺を不燃ゴミや粗大ゴミとして回収する制度があります。
陶器やガラス製の骨壺は不燃ゴミとして回収されることが多いですが、大型のものや特殊な材質の場合は粗大ゴミとして扱われる場合もあります。
自治体のホームページや窓口で、分類や出し方を確認しましょう。
また、遺骨が残っている場合は供養を済ませてから処分するのが望ましいです。
一部の自治体では、供養を含めた処理を行ってくれる場合もあるため、問い合わせてみると良いでしょう。
寺院や供養業者に依頼する
寺院や供養業者に依頼すると、骨壺を適切に供養したうえで処分できます。
納骨を終えた後の骨壺は、供養のためにお焚き上げを行う寺院や業者で引き取ってもらえることが多いです。
費用は5,000円~20,000円程度で、供養の内容によって変わります。
特に故人を大切に供養したい場合は、宗派やお寺の対応を確認するとよいでしょう。
また、骨壺と一緒に位牌や遺品をまとめて供養してもらうことも可能な場合があります。
専門業者に引き取ってもらう
専門業者に依頼すれば、骨壺を適切な方法で引き取ってもらえます。
墓石業者や遺品整理業者の中には、骨壺の回収や供養、さらにはリサイクルまで対応しているところもあります。
特に金属製や特殊な材質の骨壺は一般の自治体回収では処分が難しいため、専門業者に依頼するのが安心です。
費用は5,000円~15,000円程度が相場で、供養の有無や業者のサービス内容によって異なります。
リサイクル・再利用する
骨壺の素材によっては、リサイクルや再利用が可能です。陶器やガラス製の骨壺は、細かく砕いて植木鉢や装飾品に加工することが可能です。
また、一部の専門業者では、骨壺を別の用途にリメイクするサービスを提供しています。
金属製の骨壺は、金属回収業者に依頼すれば資源として再利用されることもあります。
環境に配慮しつつ、故人の思い出を大切に残したい場合には、リサイクルや再利用を検討するのも良い方法です。
骨壺の処分費用の目安
骨壺の処分費用の目安は、下記の通りです。
処分方法を選ぶ際の参考にしてください。
| 処分方法 | 費用の目安 |
|---|---|
| 不用品回収業者に回収してもらう | 3,000円~10,000円 |
| 自治体のルールに従って処分する | 無料~数百円(自治体による) |
| 寺院や供養業者に依頼する | 5,000円~20,000円(供養付きの場合) |
| 専門業者に引き取ってもらう | 5,000円~15,000円 |
| リサイクル・再利用する | 業者により異なる(要相談) |
遺骨を手放す手順
遺骨を手放す手順は、下記の通りです。
- 遺骨の処分方法を決める
- 寺院や霊園、業者に相談して手続きを確認する
- 必要に応じて遺骨をパウダー状にする
- 遺骨を選んだ方法で供養・処分する
- 遺骨を処分した証明書が必要な場合は取得する
遺骨の処分方法は、故人や遺族の意向を尊重しながら慎重に決めることが重要です。納骨や散骨、手元供養など、選択肢は多岐にわたります。
また、自治体のルールや業者の手続きも確認し、トラブルなく適切に供養を行いましょう。
骨壺を砕いて処分する手順
骨壺を砕いて処分する手順は、下記の通りです。
- 骨壺の材質を確認する
- 作業場所を確保し、保護具を着用する
- 骨壺を布や新聞紙で包む
- ハンマーなどを使って骨壺を砕く
- 自治体のルールに従って処分する
順を解説します。
1.骨壺の材質を確認する
骨壺の材質を確認することは、安全に処分するための重要なステップです。
骨壺には主に陶器、ガラス、金属、木製などさまざまな種類があり、それぞれ適した処分方法が異なります。
陶器やガラス製のものは砕くことで自治体の不燃ごみとして処理できることが多いですが、金属製のものは専門業者に依頼する必要があります。
また、木製の骨壺は焼却可能な場合が多いです。
骨壺の底や側面には材質の表示があることが多いため、まずはラベルや刻印を確認しましょう。
処分方法を誤ると自治体で回収されない場合もあるため、事前に確認し、適切な手段で処分することが大切です。
2.作業場所を確保し、保護具を着用する
骨壺を砕く際は、周囲に危険が及ばないよう適切な作業場所を確保することが重要です。屋外の広いスペースや、換気の良いガレージなどを選ぶと安全です。
作業中は破片が飛び散る可能性があるため、保護具の着用が必須。厚手の手袋や安全ゴーグルを使用し、必要に応じてマスクを着用すると安心です。
また、作業中に転倒やケガを防ぐため、滑りにくい靴を履くこともおすすめします。
作業スペースには飛散防止用のシートを敷き、周囲に壊れやすいものがないことを確認してから作業を開始しましょう。
3.骨壺を布や新聞紙で包む
骨壺を砕く際には、破片が飛び散らないようにするために、しっかりと布や新聞紙で包むことが重要です。
特に陶器やガラス製の骨壺は細かく砕けやすいため、包み方によって安全性が大きく変わります。
厚手の布や何重にも重ねた新聞紙を使用し、できるだけ骨壺が動かないように固定しましょう。
また、布や新聞紙で包んだ後、ガムテープやひもでしっかりと留めると、作業中にずれる心配がなくなります。
飛散防止のためにビニール袋に入れる方法も有効です。こうすることで、作業の安全性を確保しながら、自治体の処分ルールに適した形で処理を進めることができます。
4.ハンマーなどを使って骨壺を砕く
骨壺を砕く際は、慎重に作業を進めることが重要です。
まず、ハンマーや金槌などの適切な工具を用意し、衝撃を分散させるために骨壺を布や新聞紙で包んだ状態で作業を行いましょう。
破片が飛び散らないように、骨壺を段ボール箱の中に入れて砕くのも有効です。
ハンマーを振るう際は、ゆっくりと力を加え、少しずつ砕いていくことが安全に処理するコツ。
特に陶器やガラス製の骨壺は破片が鋭利になりやすいため、注意が必要です。
作業後は破片が広がらないよう慎重に回収し、自治体のルールに従って処分しましょう。
5.自治体のルールに従って処分する
骨壺を砕いた後は、自治体のルールに従って適切に処分しましょう。
多くの自治体では、陶器やガラスの破片は不燃ゴミとして処理されますが、大きな破片がある場合は粗大ゴミ扱いになることもあります。
自治体のホームページや役所に確認し、適切なゴミの分別方法を把握しておくことが重要です。
破片を安全に回収し、新聞紙や厚手の袋で包んでから指定の回収日に出しましょう。
また、金属製の骨壺は金属ゴミ、木製の骨壺は可燃ゴミとして処理されることが多いため、材質ごとの分別も忘れないようにしてください。
適切な処分方法を選ぶことで、安全かつ環境に配慮した対応ができます。
骨壺の処分が必要になるシーン
最後に骨壺の処分が必要になるシーンを2つ紹介します。
当てはまる方は、ぜひチェックしてください。
納骨後に不要になったとき
納骨後、骨壺が不要になることがあります。
多くの霊園や寺院では、納骨時に遺骨を骨壺から取り出し、合祀墓や納骨堂に納めるため、骨壺が手元に残る場合があります。
このような場合は、供養を行ったうえで処分するのが適切です。
寺院や供養業者に依頼してお焚き上げをしてもらう方法や、不用品回収業者に依頼する方法があります。
自治体によっては不燃ごみとして回収できる場合もありますが、事前にルールを確認し、適切に処分しましょう。
環境や宗教的な観点からリサイクルを検討するのも一つの選択肢です。
墓じまいで不要になったとき
墓じまいを行う際、遺骨を取り出した後の骨壺が不要になることがあります。
墓石の撤去とともに骨壺を処分するケースが多いですが、供養を済ませた上で適切に処分することが大切です。
多くの寺院や霊園では、お焚き上げ供養を行いながら骨壺を引き取ってくれるサービスを提供しています。
また、遺品整理業者や不用品回収業者に依頼することで、安全かつ迅速に処分することが可能です。
自治体によっては不燃ごみや粗大ごみとして処理できる場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。
墓じまい後の遺骨は、新たな納骨堂や合祀墓、散骨などの方法で供養することが一般的です。
骨壺ほか遺品の処分は「不用品なんでも回収団」へおまかせ!

「不用品なんでも回収団」では、骨壺の回収・供養付きの処分サービスを提供しています。
仏具や遺品整理のプロが対応し、ご遺族の気持ちに寄り添ったサービスを提供します。
骨壺と同時に遺品整理も行いたい方におすすめです。
ぜひ、お気軽にご相談ください。