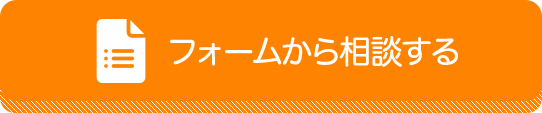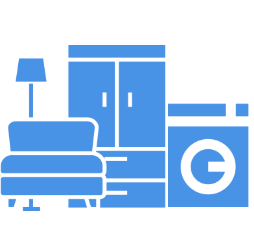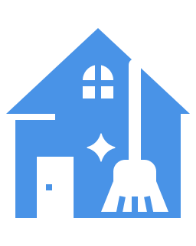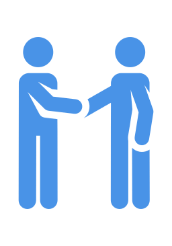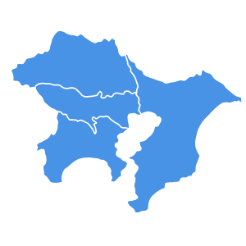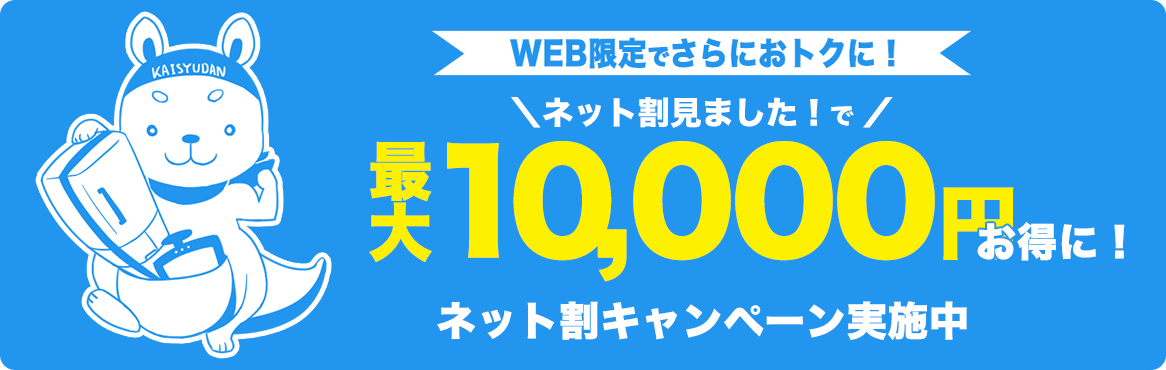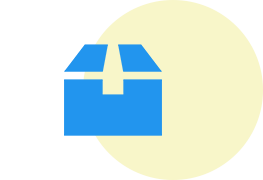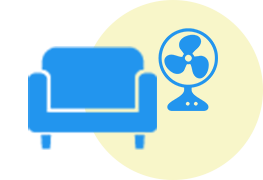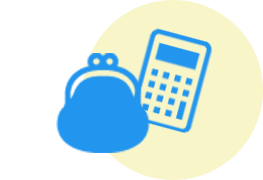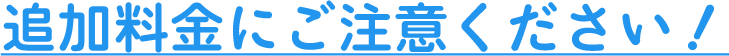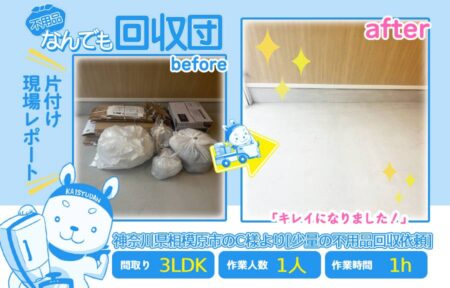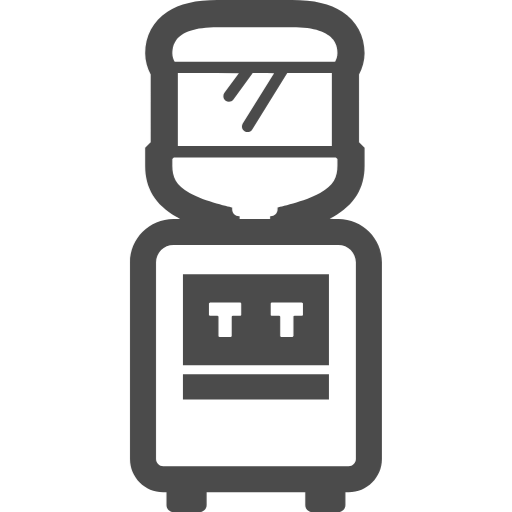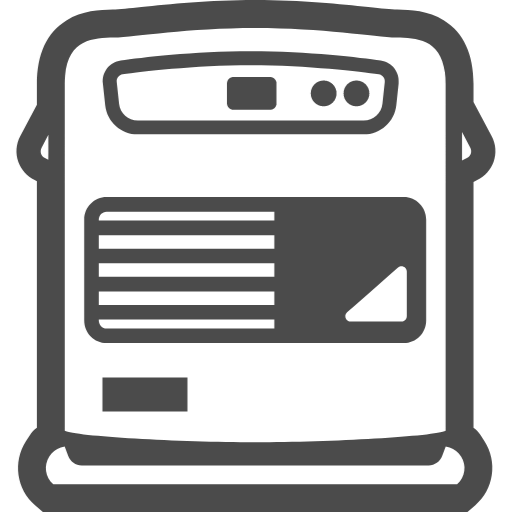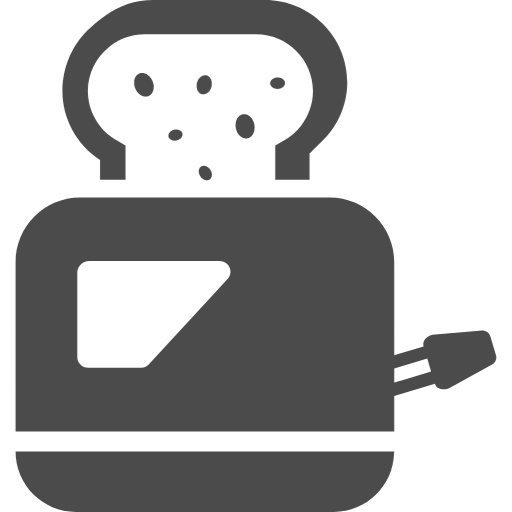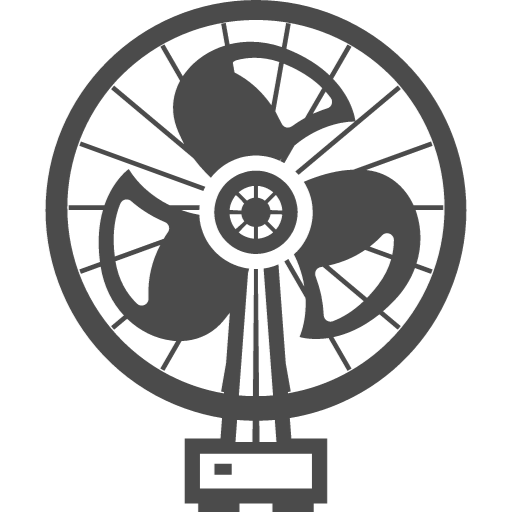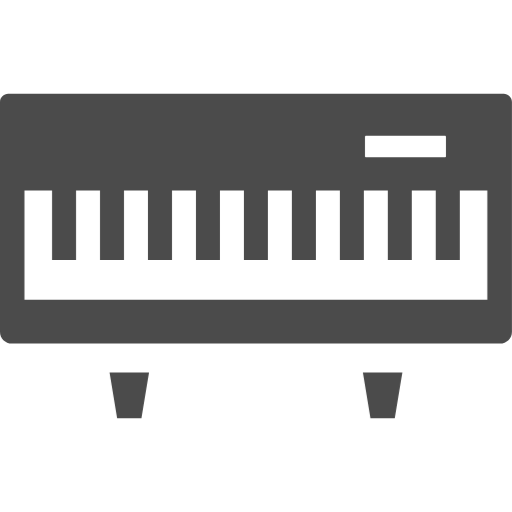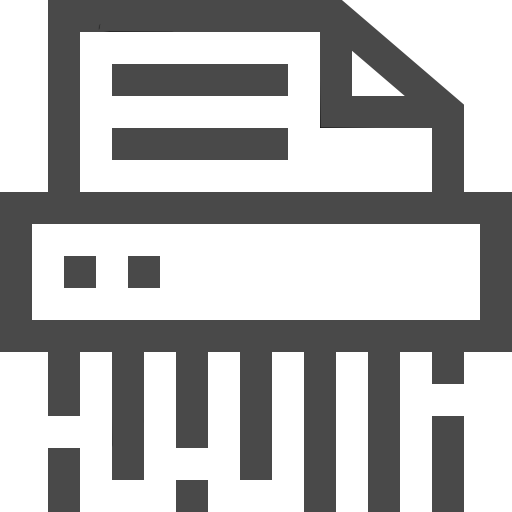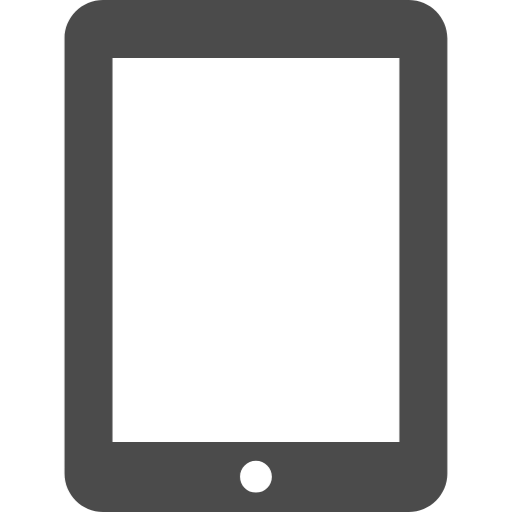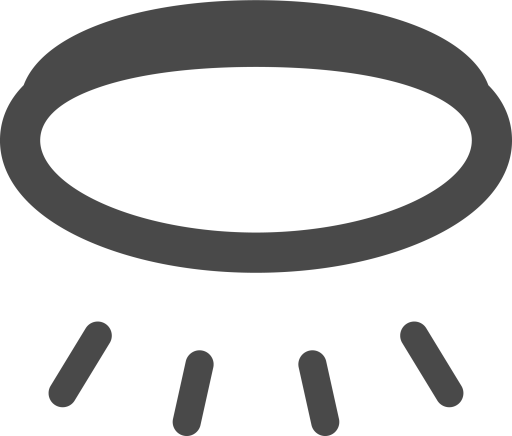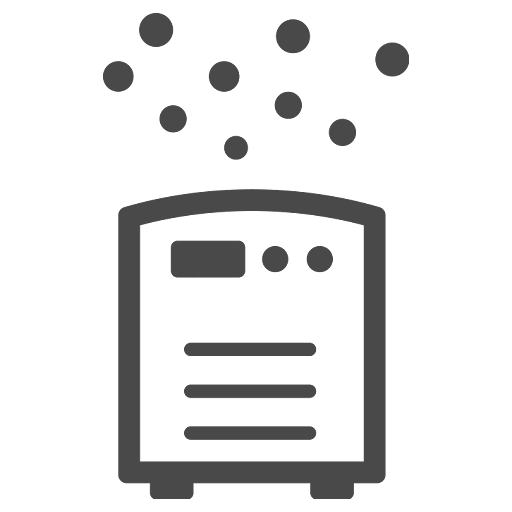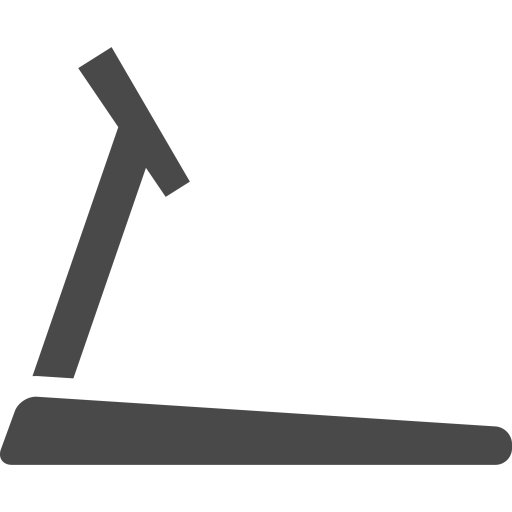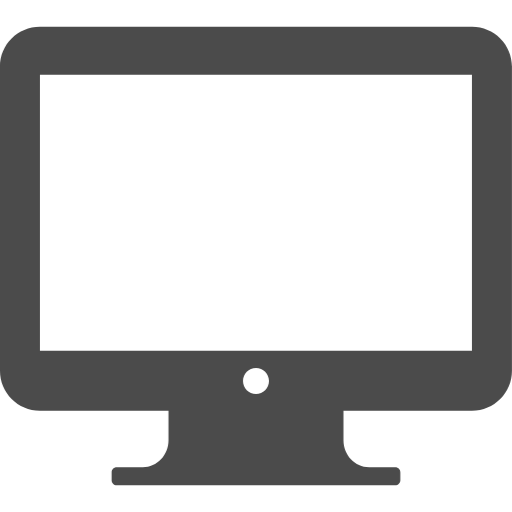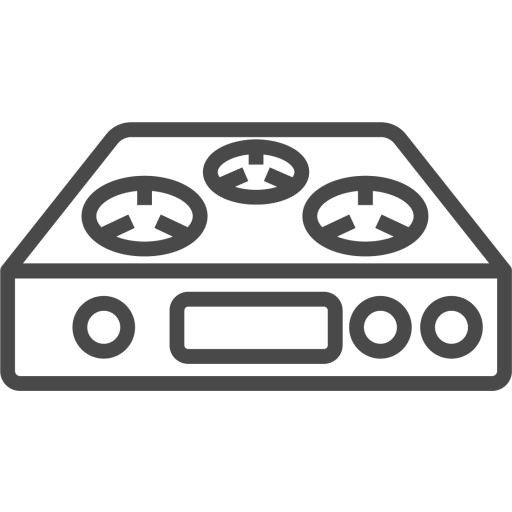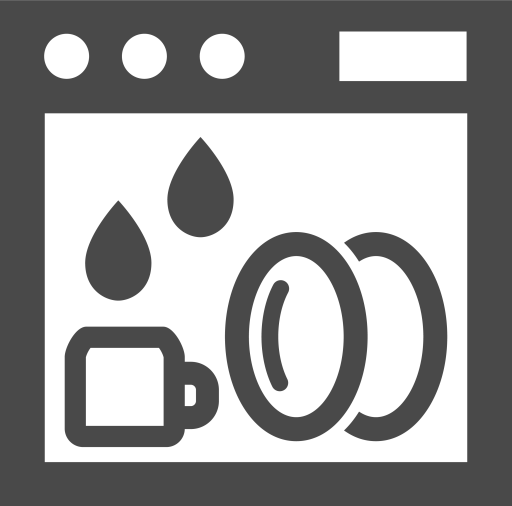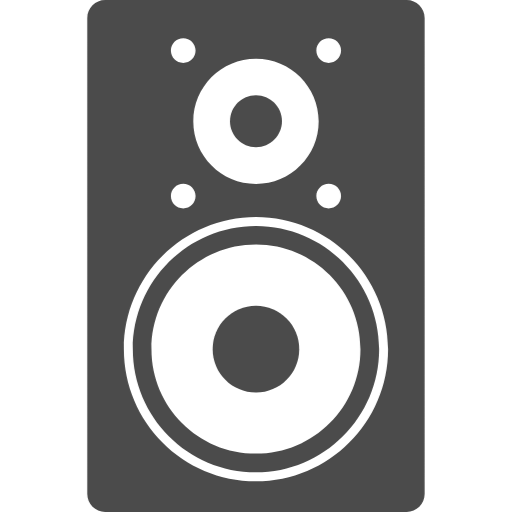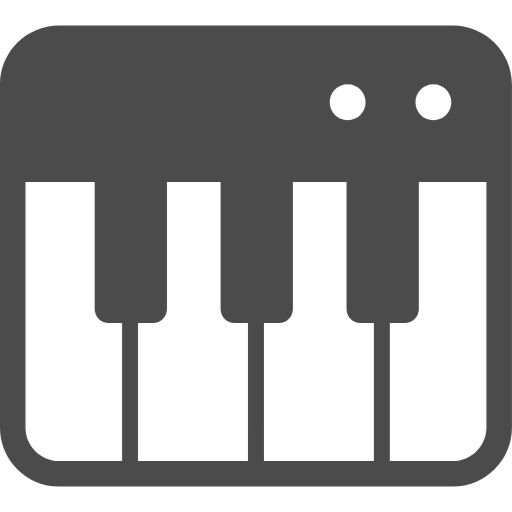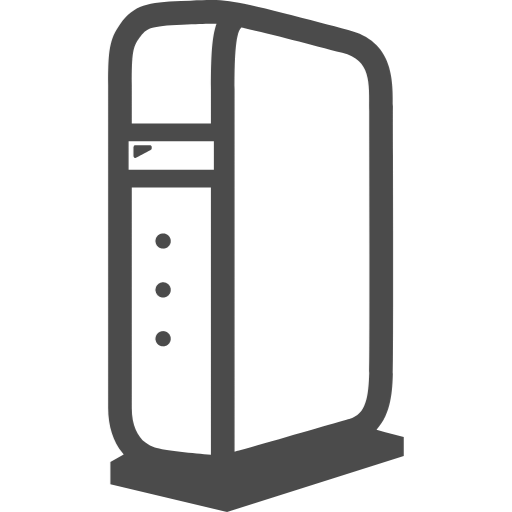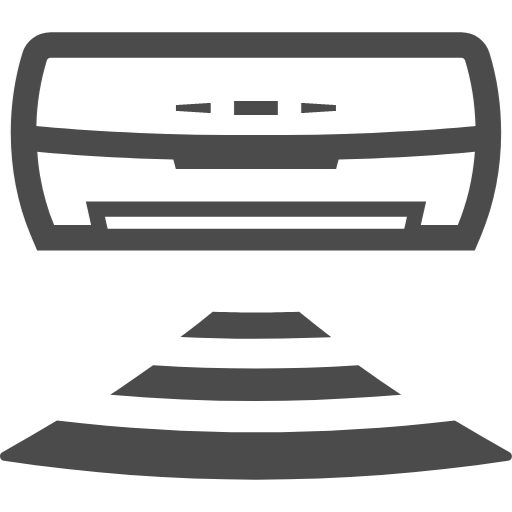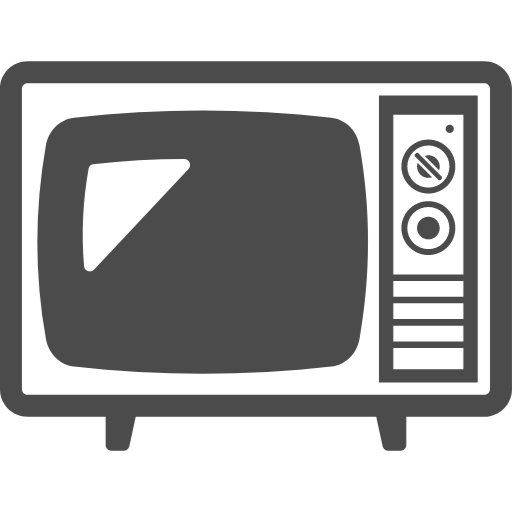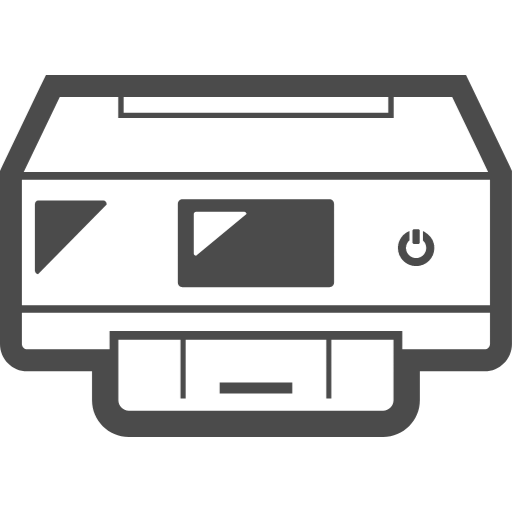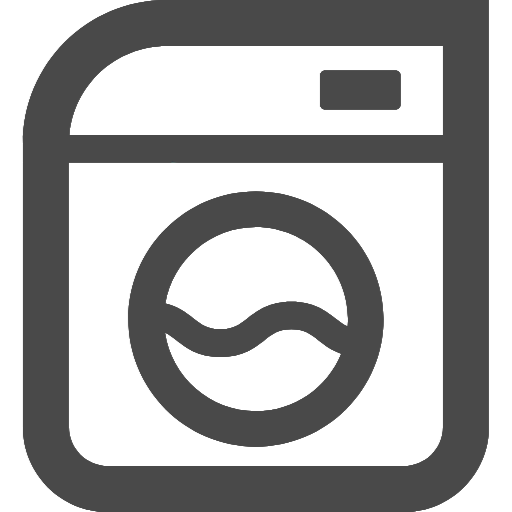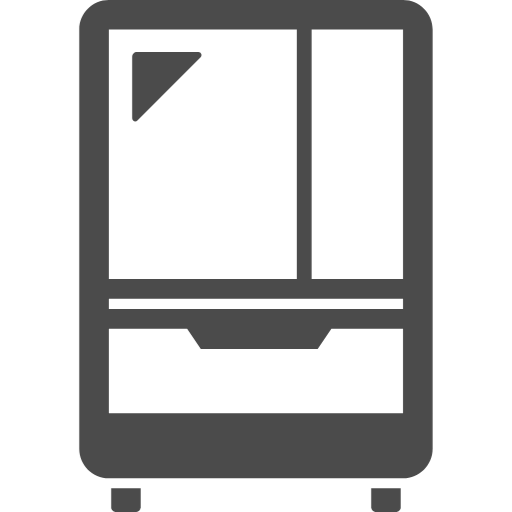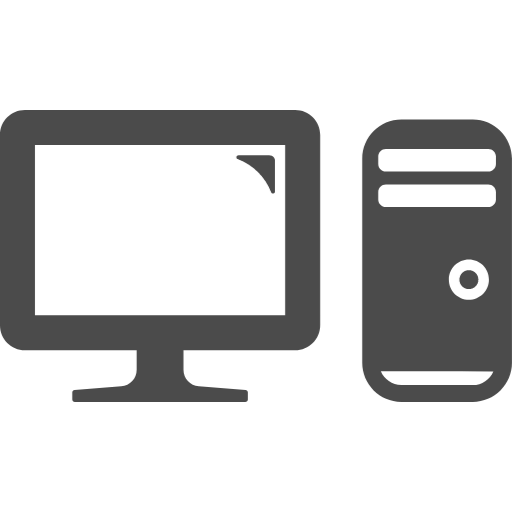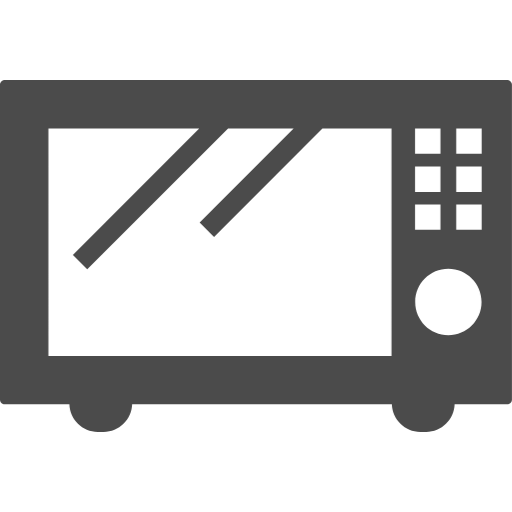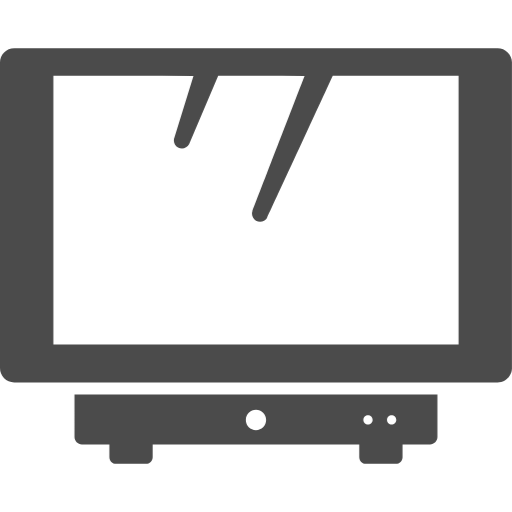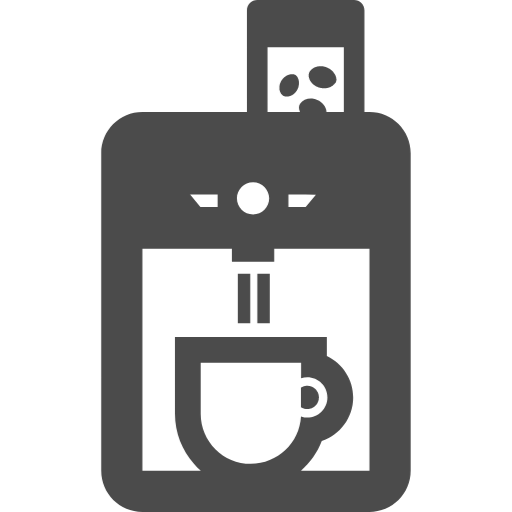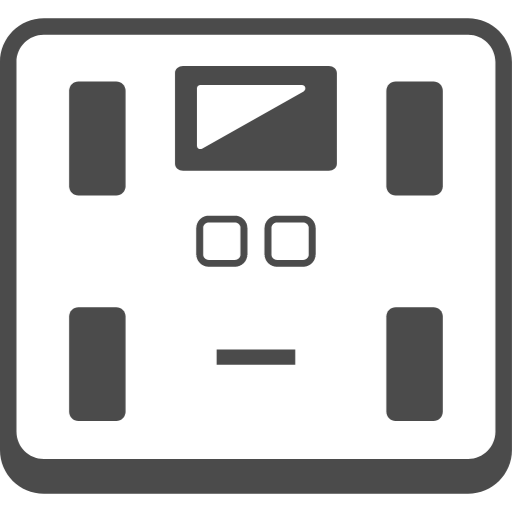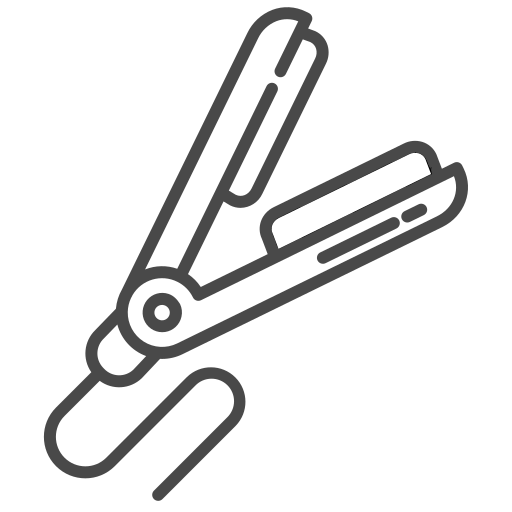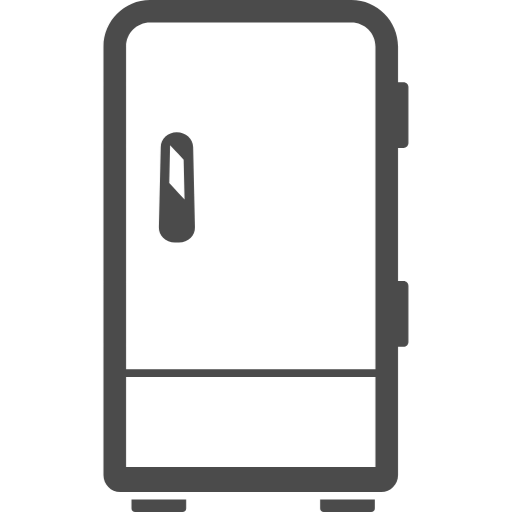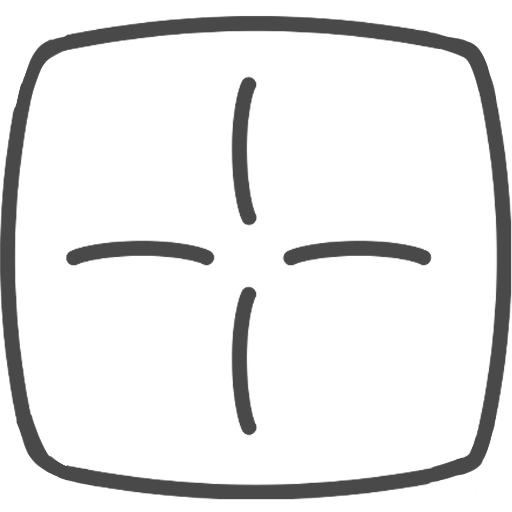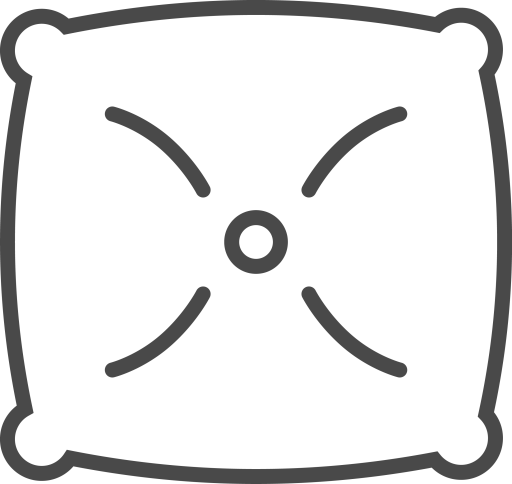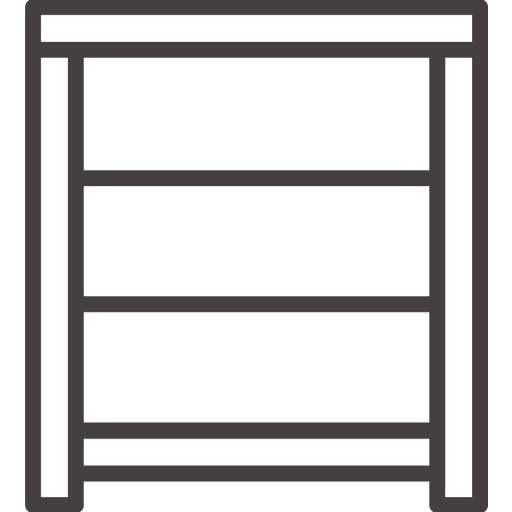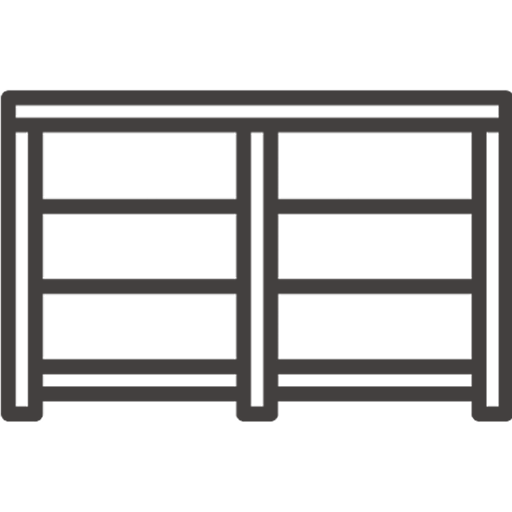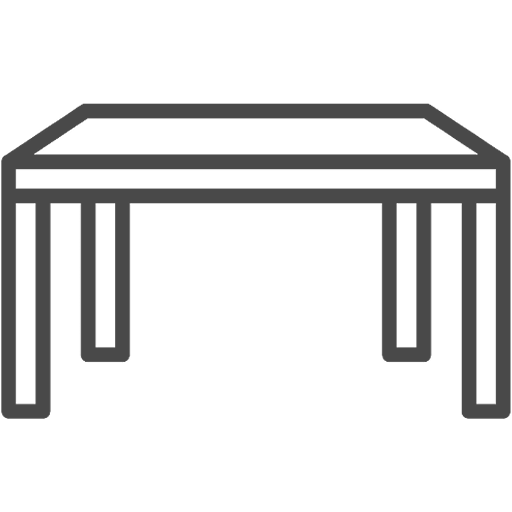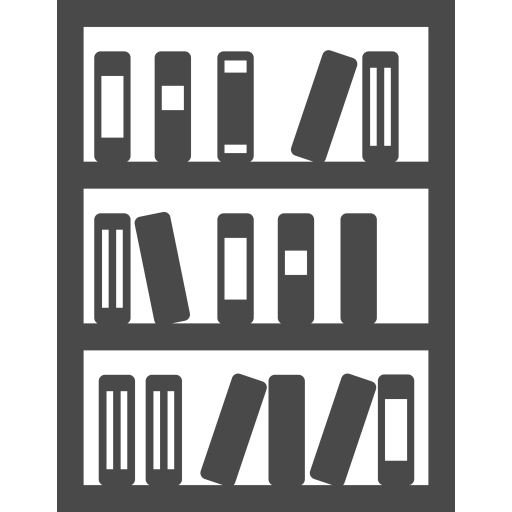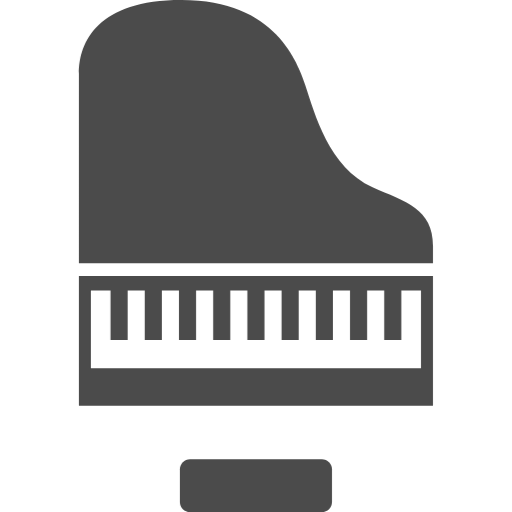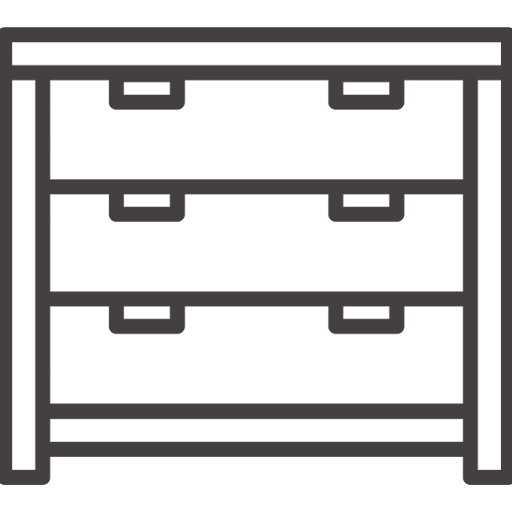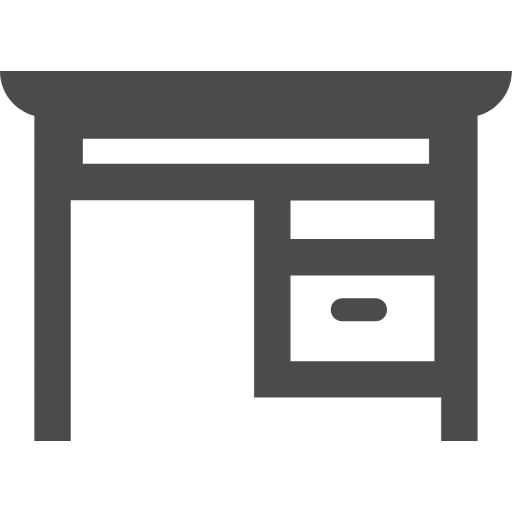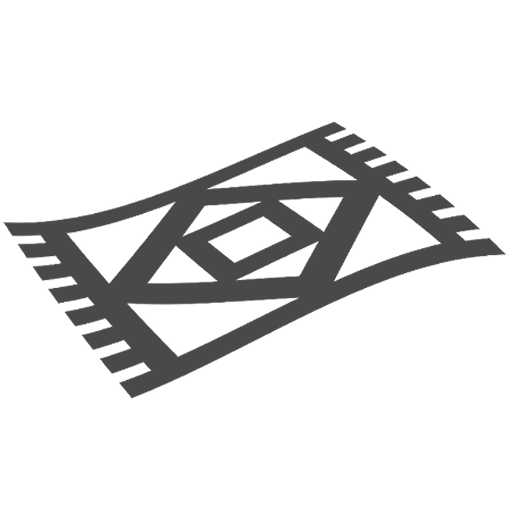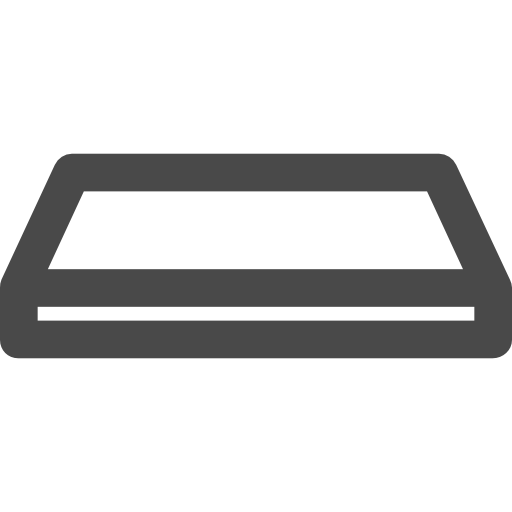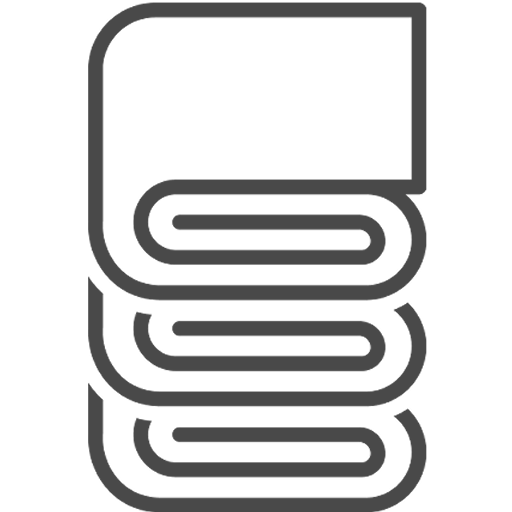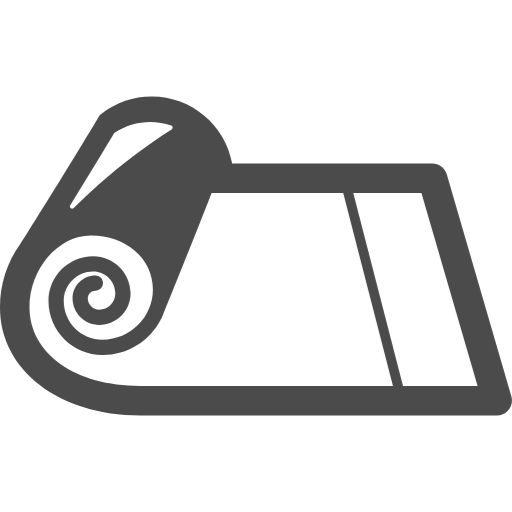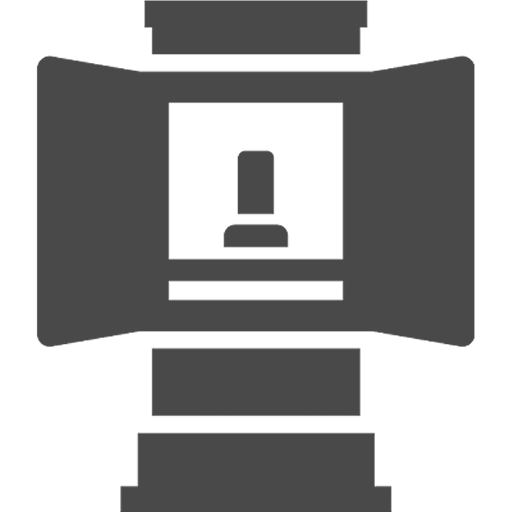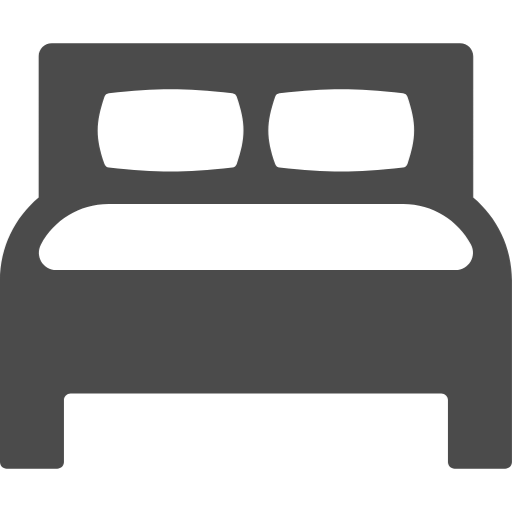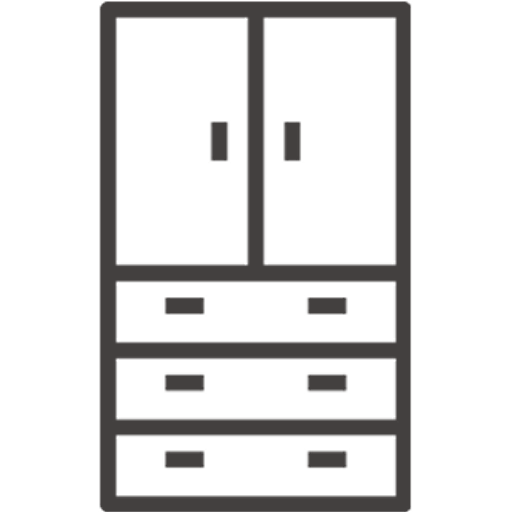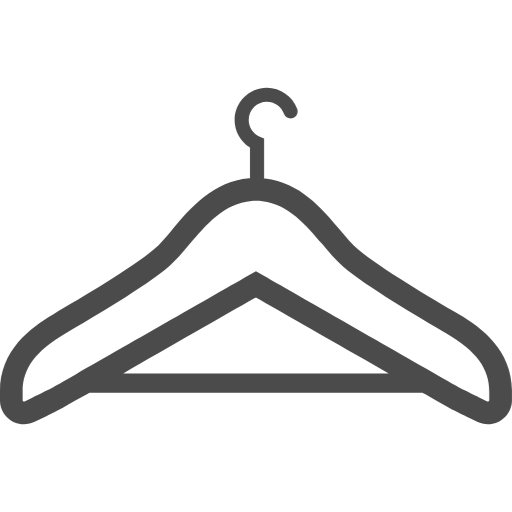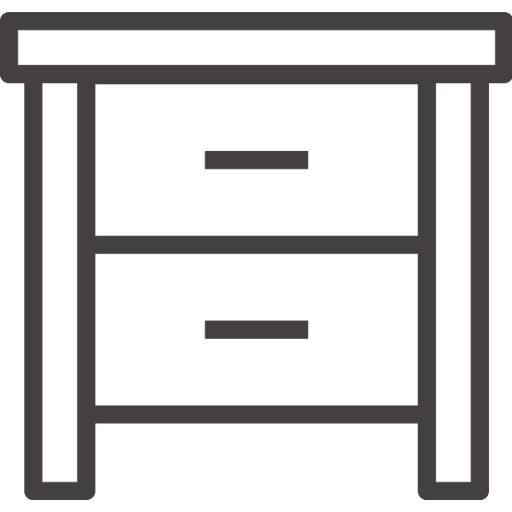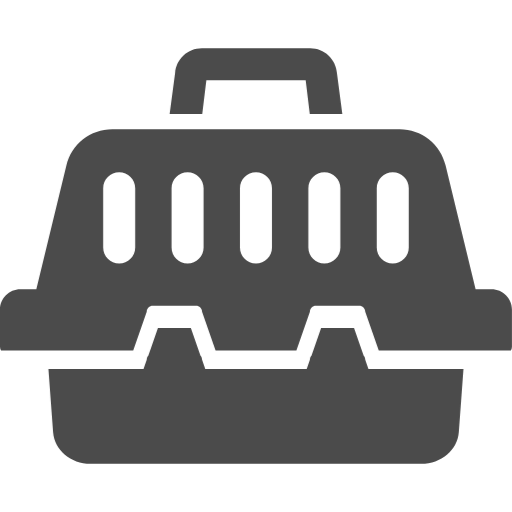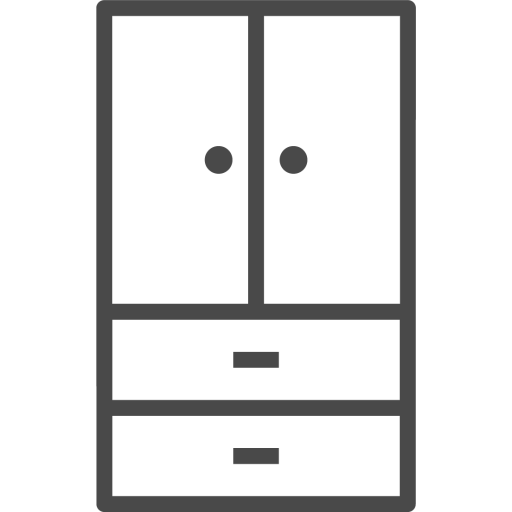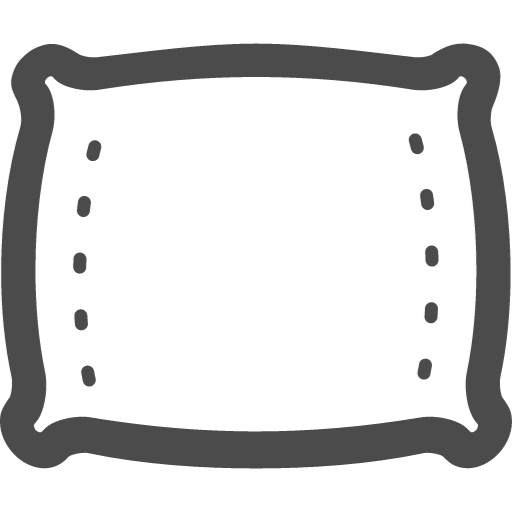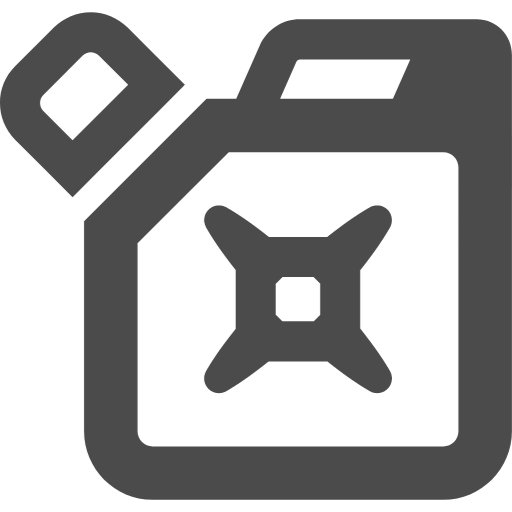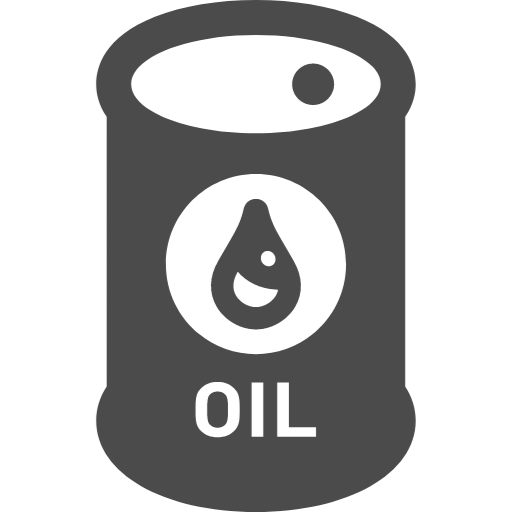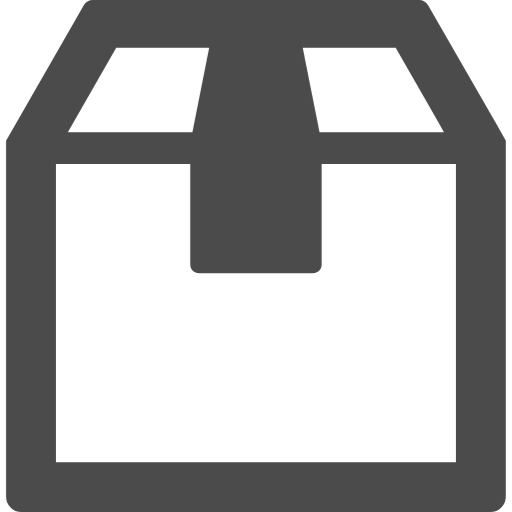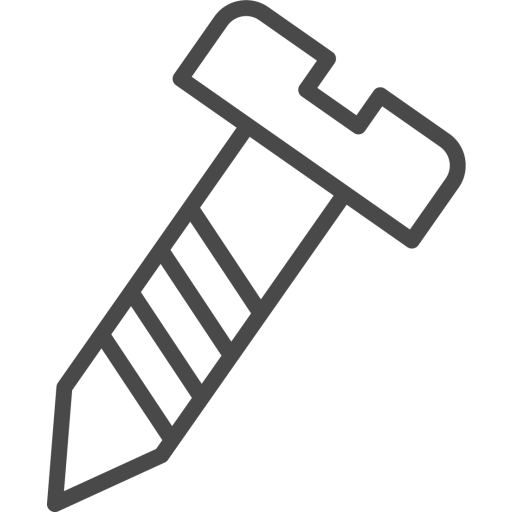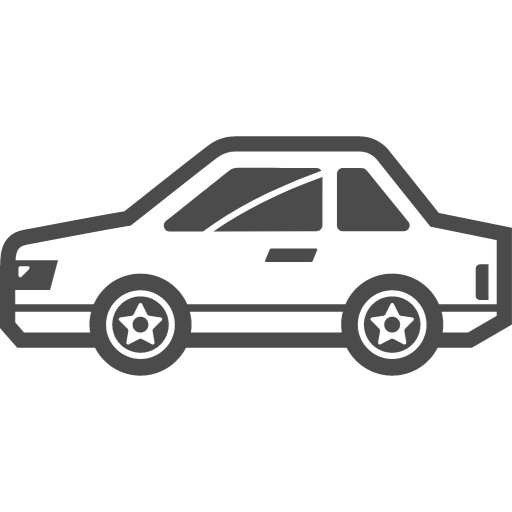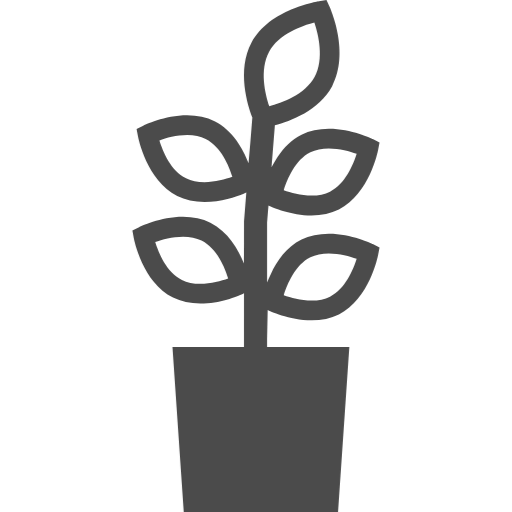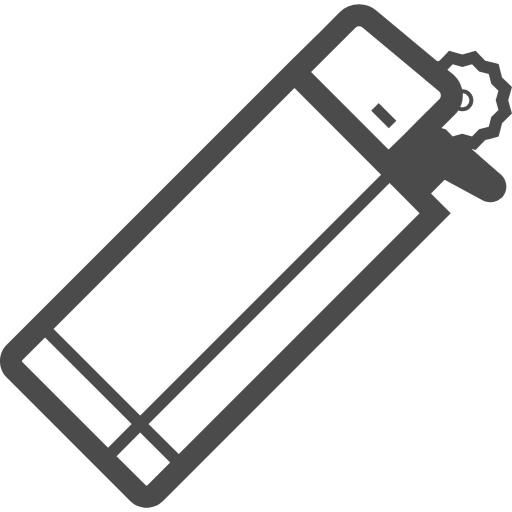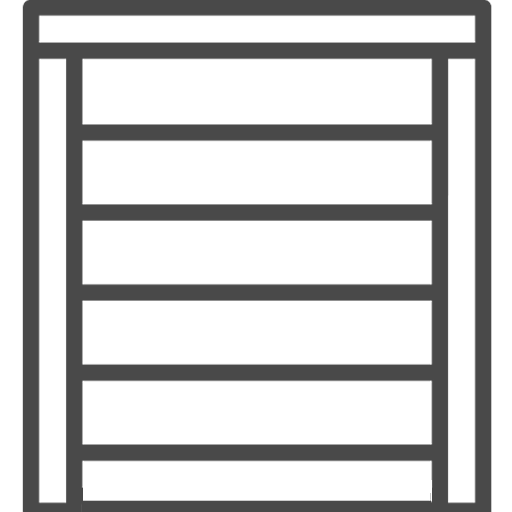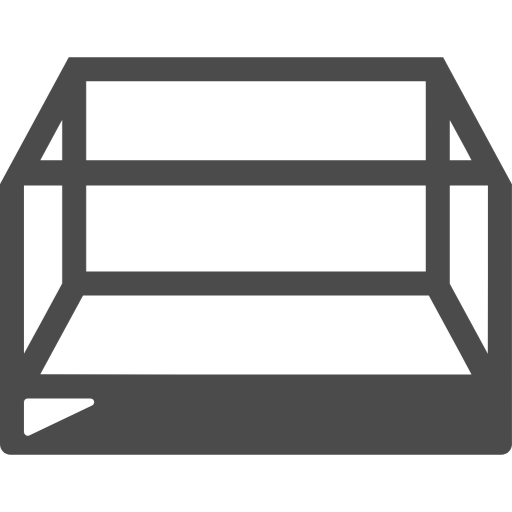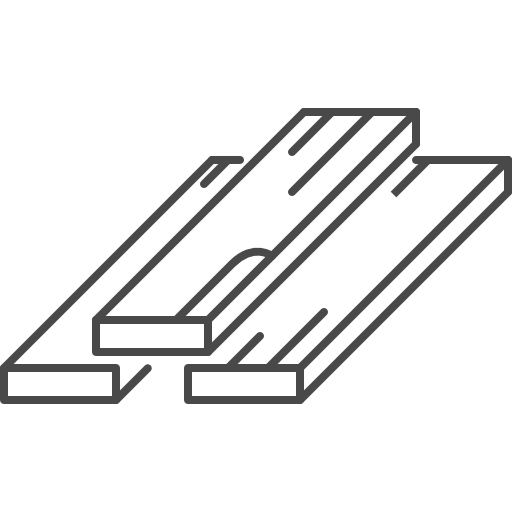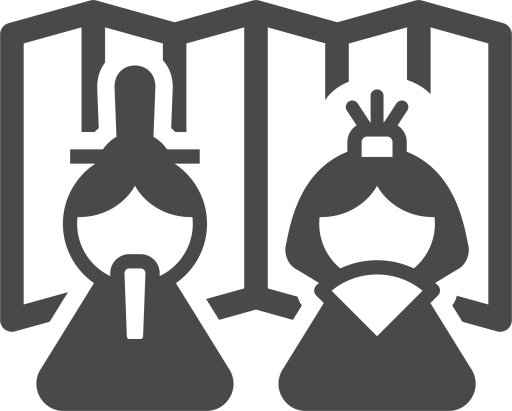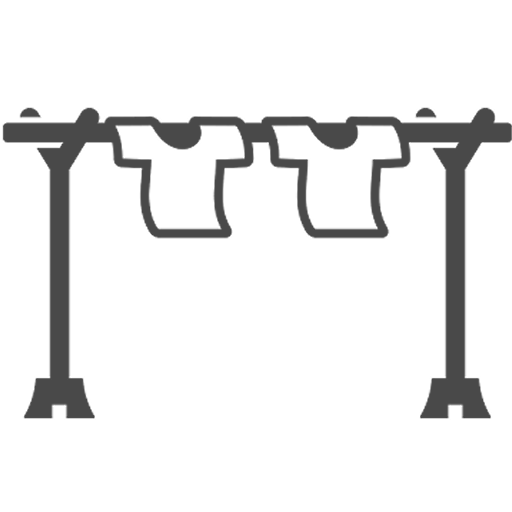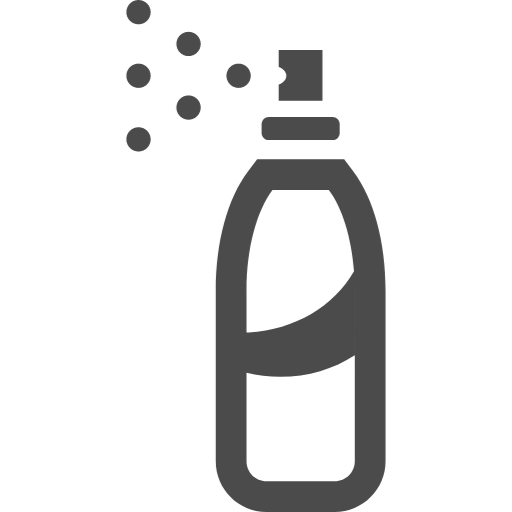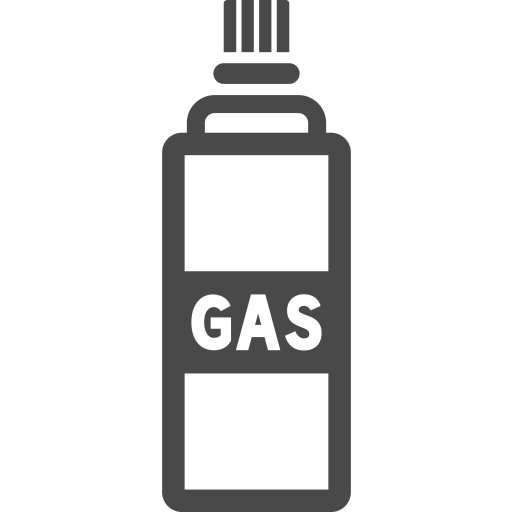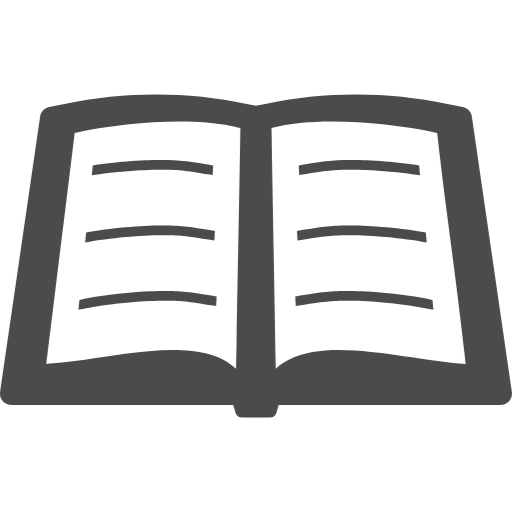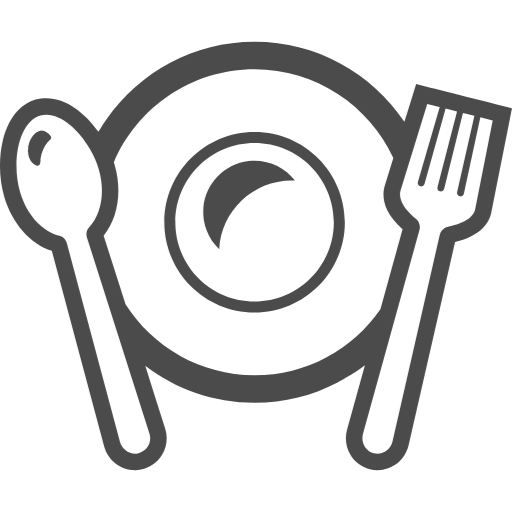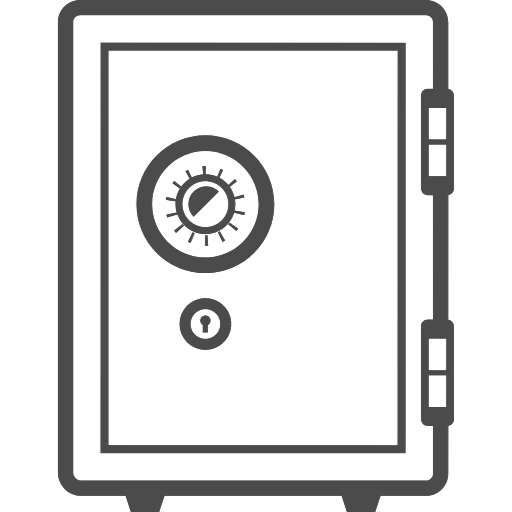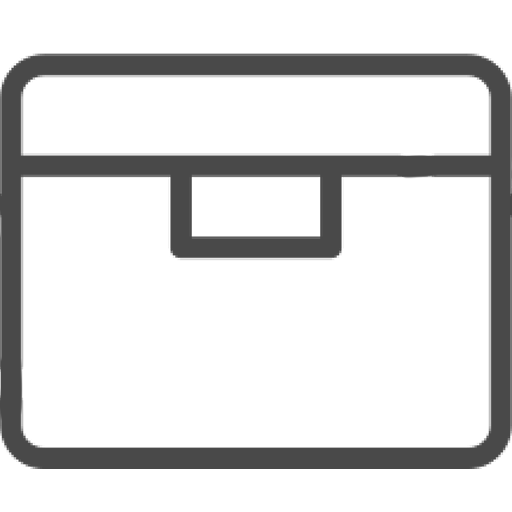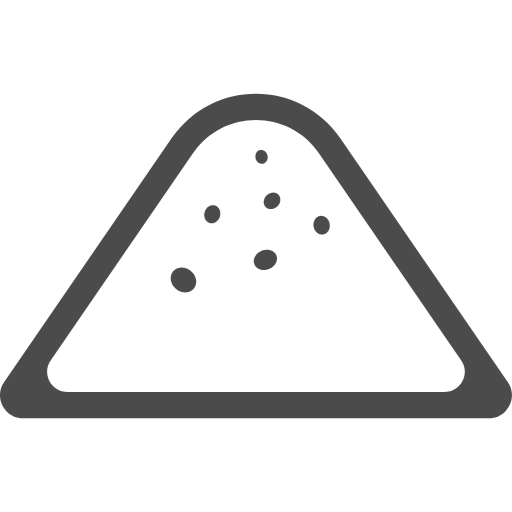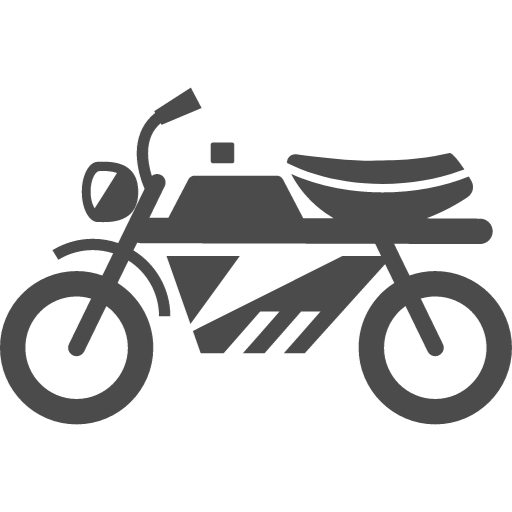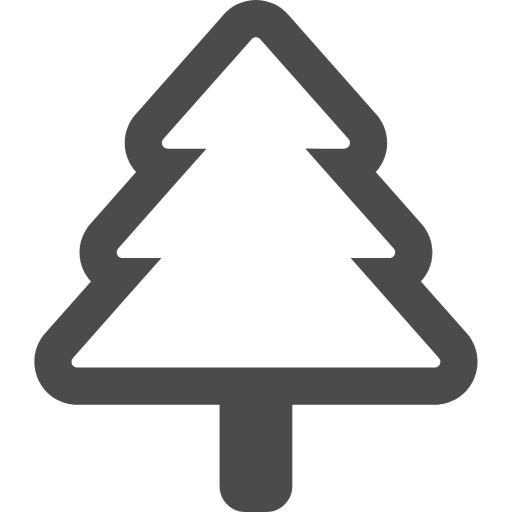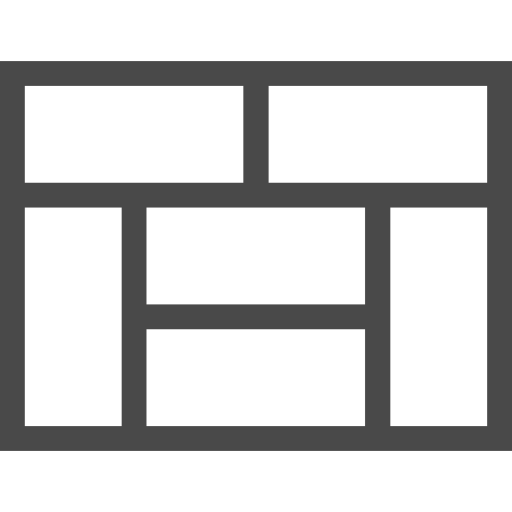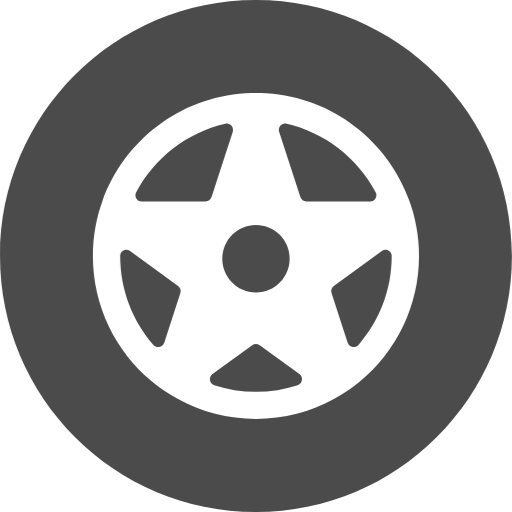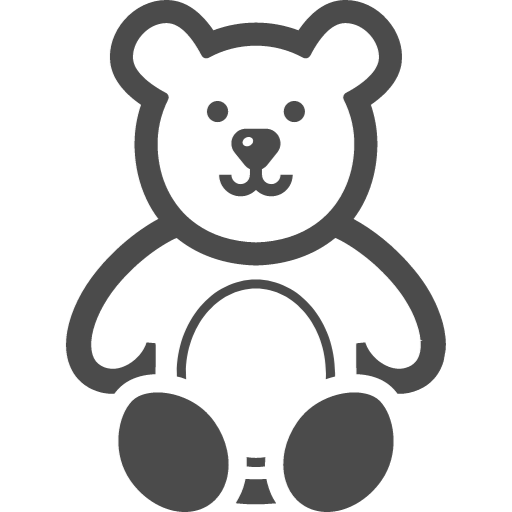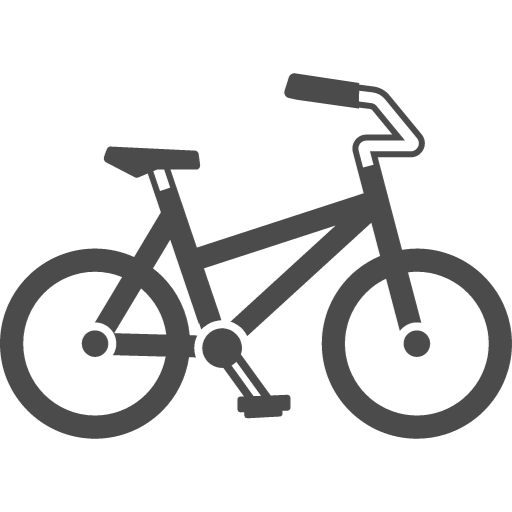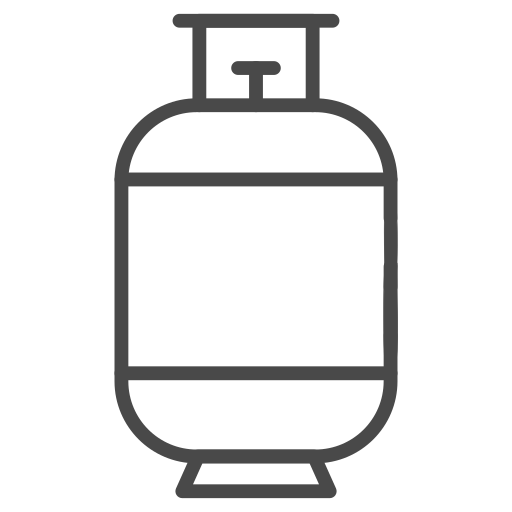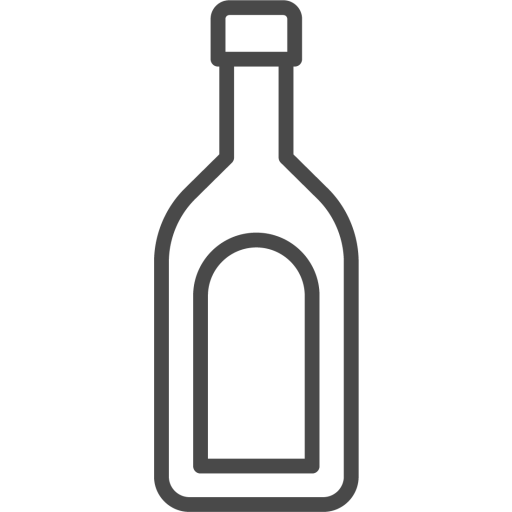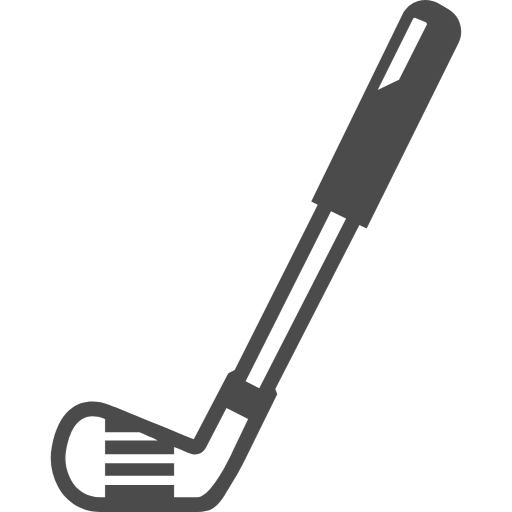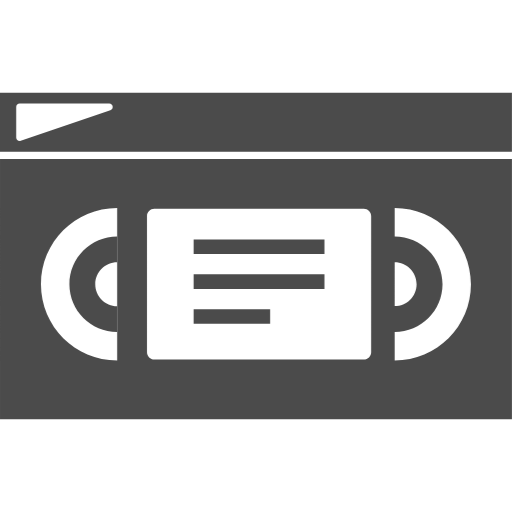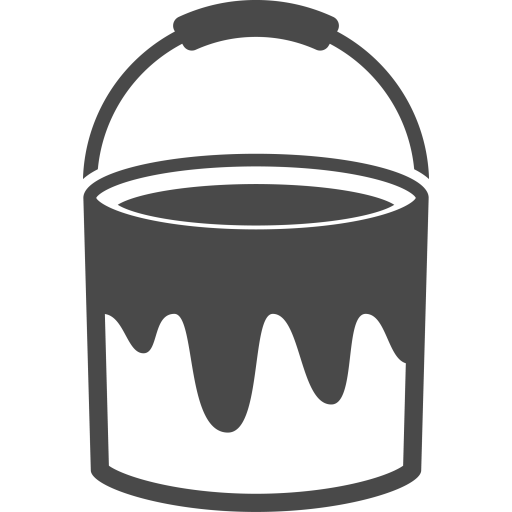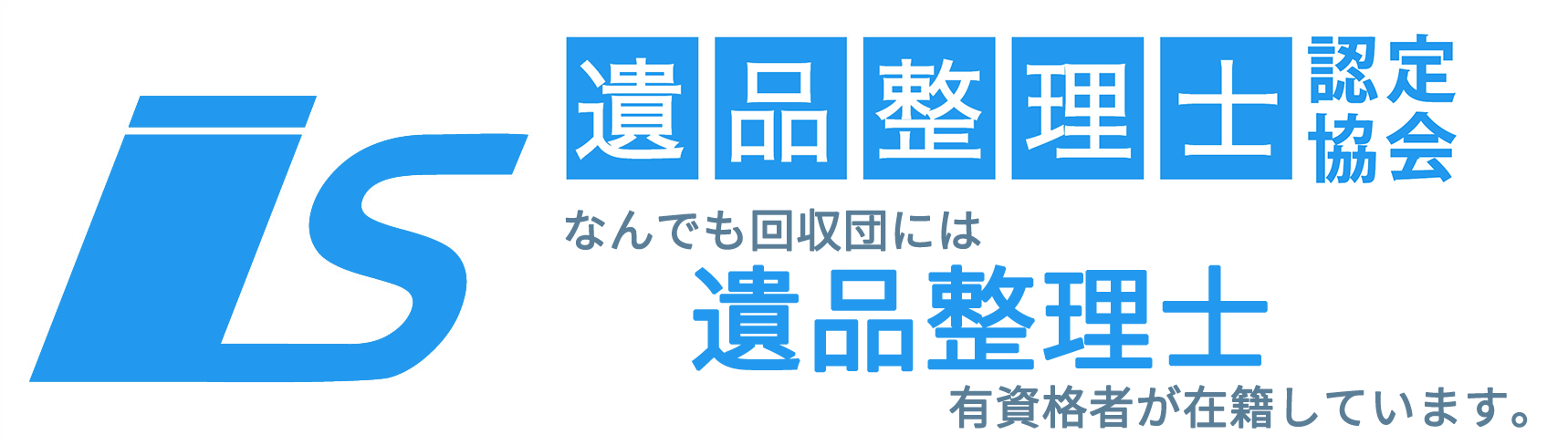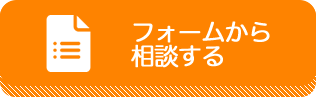片付けられない病気について解説します。
部屋を片付けられない状態が続く背景には、心や脳の病気が関係していることがあります。
本記事では、片付けられないことと病気との関係、見落としがちなサイン、セルフチェック方法、そして改善のための具体的な習慣づくりまでをわかりやすく解説。
この記事を読むことで、自分や身近な人の異変に気づき、適切な対応につなげるヒントが得られます。
ぜひ参考にしてください。
片付けられないのは病気の可能性あり
部屋が散らかっているのは「忙しいから」「疲れているだけ」と思い込んでいませんか?
確かに一時的な散らかりなら問題ありません。
ですが、長期間にわたって片付けができない状態が続く場合、単なる性格や怠け癖ではなく、心や脳の病気が関係している可能性があります。
日常生活に支障をきたしたり、人間関係や仕事に悪影響を及ぼしているなら、注意が必要です。
まずは、「なぜ片付けられないのか」を見つめ直すことが大切です。
片付けられない原因として考えられる病気
片付けられない原因として考えられる病気を、6つ紹介します。
- うつ病
- 強迫性障害
- セルフネグレクト
- 依存症
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)
- 脳の病気
うつ病
うつ病は、気分の落ち込みや無気力が続く心の病気で、日常生活にさまざまな支障をきたします。
その症状のひとつとして「片付けられない状態」が現れることがあります。
「部屋が散らかっているのに気にならない」「片付けなきゃと思っても体が動かない」
それはただの怠けではなく、うつ病によるエネルギーや意欲の低下が原因かもしれません。
「掃除をする気力がわかない」「何も手につかない」と感じる状態が何日も、もしくは何週間も続く場合は要注意。
心のSOSを見逃さず、専門機関に相談することが大切です。
強迫性障害
強迫性障害は、不安や恐怖から特定の行動を繰り返してしまう精神疾患です。
片付けに関しては、「物を手放すと不安になる」「後で必要になるかもしれない」といった強い執着があり、不要な物でも捨てられずに溜め込んでしまう傾向があります。
また、「完璧に片付けなければ気が済まない」といった思考から、片付け作業に極端なこだわりが生じるケースもあり、途中で作業をやめられず疲れ果ててしまうことも。
片付けが日常生活に支障をきたすレベルで悩みの種になっている場合は、強迫性障害が隠れている可能性があります。
セルフネグレクト
セルフネグレクトとは、自分の身の回りの世話を放棄してしまう状態で、特に高齢者や一人暮らしの人に多く見られます。
片付けられないだけでなく、食事を抜いたり入浴を怠ったり、病院に行かなくなるなど、生活全般への関心が薄れていくのが特徴です。
原因としては、うつ状態や社会的孤立、体力の低下などが関係していることが多く、本人に「このままではまずい」という自覚がないケースも少なくありません。
部屋が荒れていても何の対処もできず、日常生活に明らかな支障が出ている場合は、セルフネグレクトの可能性があるため、早めの周囲の気づきと支援が重要です。
依存症
依存症は、アルコール・薬物・ギャンブル・スマートフォンなど、特定のものに過度にのめり込んでしまう病気です。
依存対象に意識や時間を奪われることで、掃除や片付けといった日常的な行動がおろそかになり、部屋が散らかったまま放置されるようになります。
また、依存によって感情のコントロールが難しくなり、無気力や判断力の低下を招くことで、さらに生活環境が悪化していく悪循環に陥るケースも。
本人に自覚がないことも多く、「やらなきゃいけないのにできない」と感じているなら、依存の兆候を疑い、専門的な支援を受けることが重要です。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)
PTSDは、事故や災害、虐待、いじめなど強い心の傷(トラウマ)を経験した後に発症する心の病気です。
フラッシュバックや不安、不眠などの症状が続く中で、日常生活を維持する気力や集中力が失われ、片付けや掃除といった行動ができなくなることがあります。
過去の記憶がよみがえる場所や物を避けるために片付けが進まない、逆に物をため込むことで安心感を得ようとするケースも。
片付けられない背景にトラウマが隠れている場合は、無理に片付けを促すのではなく、心のケアを優先する必要があります。
脳の病気
片付けられない原因として、認知症や前頭側頭型認知症などの脳の病気が関係しているケースもあります。
これらの病気では、記憶力や判断力、計画性といった認知機能が低下し、何をどこに片付ければよいか分からなくなる、片付ける必要性を感じなくなるといった状態が見られます。
特に前頭側頭型認知症では意欲の低下や無関心が目立ち、部屋が散らかっていても気にならないことがあります。
単なる物忘れや性格の問題と見過ごされがちですが、日常生活に支障が出ている場合は専門的な診断が必要です。
大人に多い「片付けられない」ケースと見逃せないサイン
片付けられないことに病気が関係している、大人に多い「片付けられない」ケースと見逃せないサインを3つ紹介します。
- 仕事や家庭が回らなくなるほど片付けられない
- 体力・メンタルの低下から部屋が荒れていく
- 病気と気づかず自己嫌悪に陥る人が多い
仕事や家庭が回らなくなるほど片付けられない
部屋が片付かないことで、仕事や家庭の生活がうまく回らなくなっていませんか?
たとえば探し物に時間を取られたり、家族との衝突が増えたり、仕事の準備ができず遅刻が続いたりと、身の回りの散らかりが直接トラブルにつながることもあります。
また、周囲から「だらしない」「片付けて」と指摘されるたびにストレスを感じ、ますます行動が鈍くなる悪循環に陥ることも。
こうした状態が続く場合、ただの整理整頓の問題ではなく、心の不調や病気が関係している可能性があります。
体力・メンタルの低下から部屋が荒れていく
一時的な疲れなら問題ありませんが、体力やメンタルの低下が原因で片付ける気力すら湧かない状態が続く場合、注意が必要です。
気づけば部屋はどんどん荒れ、片付けのハードルが上がっていく悪循環に陥ることも。
「面倒」「明日でいい」と感じる頻度が増えてきたら、それは心や体からのSOSかもしれません。
放置せず、早めに自分の状態を見直すことが大切です。
病気と気づかず自己嫌悪に陥る人が多い
片付けができないことを「自分がだらしないだけ」と思い込み、強い自己嫌悪に陥ってしまう人は少なくありません。
しかし実際には、うつ病や発達障害など、心の病気や特性が影響しているケースもあります。
我慢して自分を責め続けるのではなく、「もしかして病気かも」と視点を変えることで、必要な支援や治療につながるきっかけになります。
病気の可能性を見極めるセルフチェックポイント
病気の可能性を見極めるセルフチェックポイントを3つ紹介します。
下記に一つでも当てはまる場合は、病気の可能性も考えられるため、医療機関への受診も検討するといいでしょう。
- 片付けられない状態が「何ヶ月も」続いている
- 日常生活や人間関係に明確な悪影響が出ている
- 他の不調(眠れない・気分が沈む・無気力など)もある
片付けられない状態を改善するための習慣づくり
片付けられない状態を改善するための習慣を3つ紹介します。
- 1日5分から始める「リセットタイム」
- 気分や体調を記録して自己観察
- モノを減らす・ルールを決めるなどの工夫
1日5分から始める「リセットタイム」
片付けへのハードルが高く感じるときは、「1日5分だけ」と時間を区切って始めるのがおすすめです。
この“リセットタイム”は、1日をリセットするための短い習慣。
たとえば「寝る前に机の上だけ片付ける」「玄関だけ整える」といった、小さな行動を積み重ねていくことがポイントです。
重要なのは、完璧を目指すのではなく「今日も5分できた」という成功体験を積むこと。
最初は小さな変化でも、続けることで暮らしの質や気持ちが整い、片付けられる感覚を取り戻していけるはずです。
気分や体調を記録して自己観察
片付けがうまくいかないときは、気分や体調の変化とどのように関係しているのかを記録し、自己観察してみましょう。
「今日はイライラして何もできなかった」「頭が重くて片付ける気力が出なかった」など、簡単なメモで構いません。
記録を続けることで、自分のメンタル状態と片付け行動の相関が見えてきます。
たとえば「落ち込んだ翌日は散らかりやすい」といった傾向がわかれば、無理に頑張ろうとするのではなく、自分に合った対処法を取りやすくなります。
自分の状態を客観的に知ることは、心の整理にもつながる大切なステップです。
モノを減らす・ルールを決めるなどの工夫
片付けが苦手な人ほど、「捨てる」ことに強いストレスを感じやすいもの。
そんなときは無理に捨てようとせず、「これ以上モノを増やさない」ことから始めてみましょう。
たとえば「1つ買ったら1つ手放す」「同じ用途のモノは2つまで」といったルールを決めておくと、自然と持ち物が整理されていきます。
また、収納スペースをあらかじめ決めておき、それ以上は持たないようにするのも有効です。
減らすことに重点を置くよりも、増やさない習慣を身につけるほうが、無理なく長く続けられます。
自分に合ったルールで、散らかりにくい環境を作りましょう。
詳しくは厚生労働省の心の健康ページもご参照ください。
病気だけでなく発達障害が影響しているケースもあります。
特にADHD(注意欠如・多動症)などの発達障害は、「片付けようとしても集中できない」「手順が分からなくなる」などの特性から、部屋の整理が難しくなることがあります。
大人の発達障害のチェックリストや対処法を詳しく知りたい方はこちら!
部屋の片付けは「不用品なんでも回収団」へ!

片付けができない原因には、心や体の不調、脳の病気などさまざまな要因が関係していることがあります。
無理をせず、プロの手を借りるのもひとつの方法です。
「不用品なんでも回収団」なら、家具や家電はもちろん、細かな雑貨までまとめて回収可能。
面倒な分別も不要で、重たい荷物の運び出しもすべてお任せできます。
自分のペースで生活を整えるための第一歩として、気軽に相談してみてください。